防災会・大災害時防災行動指針
松風台大災害発生時 防災行動指針
松風台自治会防災会
2019年 6月 6日 改訂C
- 目的
本指針は、地震による大災害が発生した時に、松風台住民が在宅時にとるべき防災行動を示す。
- 防災行動フロー
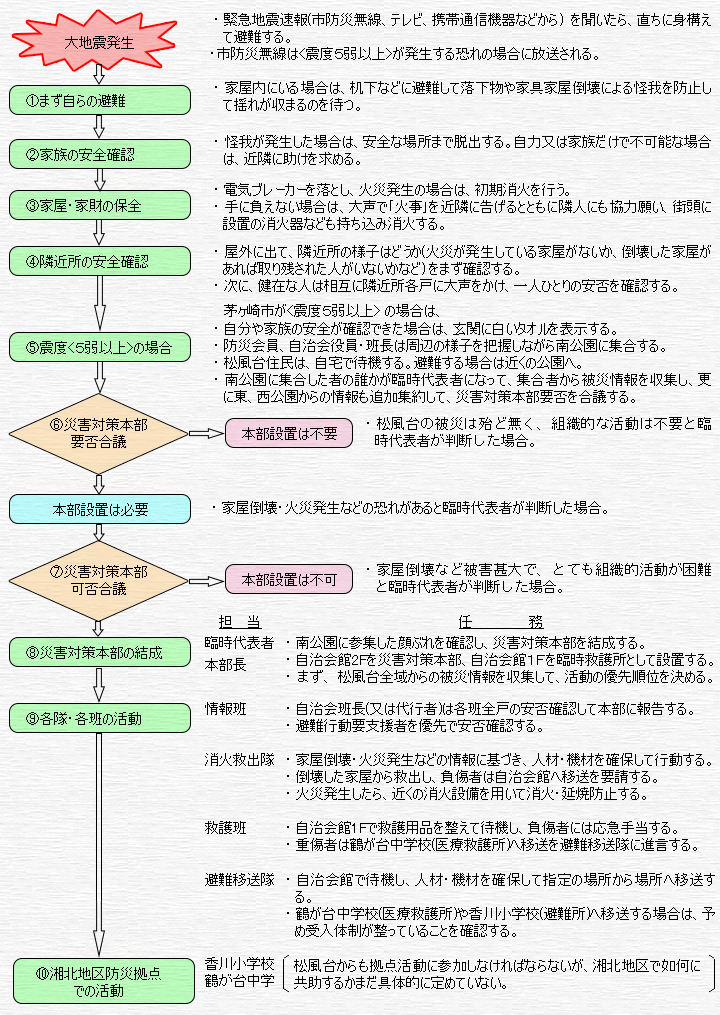
- 松風台災害対策本部の組織
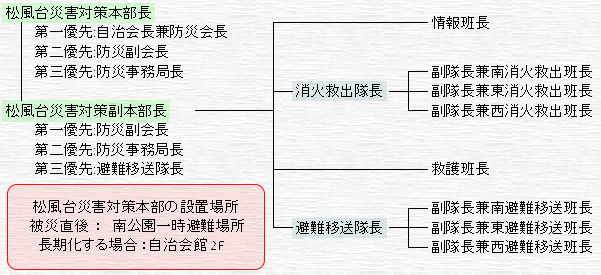
制定改訂履歴
| 制定改訂 | 年月日 | 制定のいきさつ、及び改訂箇所とその理由 |
|---|---|---|
| 制定 | 2009.03.15 | 防災ルール見直改訂諮問委員会にて従来のルールを見直し統一して制定した。
これに関連した防災会規則の改訂をもって平成21年度から適用する。 諮問委員会の活動経過、及びこの指針の制定に至った解説を残してあり今後の参考にする。 見直して廃止したルールは
|
| 改訂A | 2012.04.15 |
|
| 改訂B | 2017.03.12 | 防災会規則改訂Hによる組織構成員の簡素化に伴い、役割分担などを改訂。
|
| 改訂C | 2019.06.06 |
|
松風台大災害発生時防災行動指針の制定・改訂解説
改訂C解説 : 2019.06.06
- 題目は<指針>とする。
規程とか規則にして守らなければならないルールを作成しても、もし大災害が発生した場合には、それが本当に守ることができるかが疑問であり、臨機応変に活動しなければならく<指針>(いわゆるガイドライン)にした。
- 制定組織
この指針は、自治会全体の課題であるが、自治会役員が防災会役員トップを兼ねていることと、この指針の今後の維持管理の為には常任者のいる防災会が制定するのが妥当と考えた。
- 被災の想定と実績
神奈川県地震被害想定調査報告書 2015年05月27日公表による被害想定、及び東日本大震災2011.3.11 の被害実績の要点は下表の通り。
この被害想定は数年ごとに更新されています。
茅ヶ崎市の代表的
地震想定・実績茅ヶ崎市の被害想定 松風台における防災活動への期待 死者数 全壊家屋数 火災焼失数 【震度7】想定
大正型関東地震
可能性は少ないがゼロではない。市内 940名
松風台 7名市内 15,950棟
松風台111棟市内12,000棟
松風台 84棟- 組織的な活動はとても困難で期待できないと想定されます。
- 従って、健在で残った人々が隣近所でできる限りの救助活動をお願いします。
【震度6弱】想定
東海地震
いつ発生しても不思議ではない。わずか わずか わずか - この行動指針に定めた通りに活動が可能と思われる。
- 耐震性の低い木造住宅は倒壊するものもあり、室内では固定していない家具が移動したり倒れるものもある。
- 負傷者が発生するかもしれない。
【震度5弱】実績
東日本大震災
2011.3.11
pm2:46 発生なし なし なし - 自治会館に集合した災害対策本部要員4名で合議した結果、被害なしと判断・解散した。
- 本部要員集合率=4名/12名= 約3割
茅ヶ崎市発表では、 - 避難所に計2,040名受け入れたが人的被害なし
- 建造物と道路に若干の被害発生
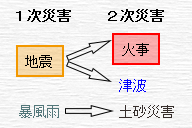
松風台では、
- 地震時は、最優先で発生予防、発生したら初期消火を。
- 平常時も、火災クラスターに囲まれ 失火/糸魚川大火(2016.12.22) の予防が必要。
- 海岸から5Km,海抜10m の位置にあり被災の可能性は少ない。
- 急傾斜地で崩壊の恐れがスリーハンドレッドゴルフ場西側にあり、ここの通行は避ける。
- 防災行動フロー
大災害発生時には、この指針を読みながら行動する訳はないので、行動フローは松風台住民全体を対象に、A4用紙1枚で簡潔明瞭にした。
従って松風台全戸配布した 防災会だより第42号 「松風台の大災害~地震・火事などに備えて~」に掲載した内容とほぼ同じで基本的なフローは一貫しています。
- 災害対策本部の設置判断の経過
- 制定時
- 行動指針制定前までは、自治会長が松風台の被災状況を判断して宣言することになっていたが、自治会長が常に在住で健在かは不明・不定であり、宣言したことを如何に住民に伝えるかも困難であった。
- 茅ヶ崎市では<震度5弱以上>の地震が観測されると配備職員は定められた地区防災拠点に参集して活動することになっており、行政の行動基準に合わせて震度5弱以上の地震をもって本部を設置することにした。
- 改訂A
- 東日本大震災時2011.3.11の教訓により、設置の判断方法と設置場所について改訂した。
- 設置の判断方法
茅ヶ崎市は震度5弱のゆれが発生したが、幸いにも松風台は屋内の物が転倒した程度で被害報告はなかった。
防災会役員4名が自治会館に参集し合議した結果、本部設置は不要と判断して解散した。
震度のみで自動的に定めるよりも、松風台周辺の被災状況を確認した結果で合議のうえ、本部設置の要否・可否を決定する手順に変更した。
- 設置の場所
本部要員はいきなり自治会館に閉じこもるよりも、南公園に集合して、進行中の被災状況や防災会員の参集状況などを把握して、長期化する場合は自治会館に移すことにした。
- 制定時
- 消火活動と人命救助とどちらが優先か?
二者択一の場合には火災クラスター延焼予防の為の消火活動を最優先とするが、近隣の人の応援も得て出来るだけ並行して人命救助も行う。
- 災害対策本部の組織
- 防災要員の参集率
- 東日本大震災時に自治会館への参集率=4名/12名=1/3であった。
- 防災会規則改訂Hにより、防災要員は防災会(常任者+顧問)約20名+自治会役員・班長40名=約60名になった。
- 東海地震【震度6弱】が発生した場合、若干の被災を受ければ参集率は楽観値1/5=12名、悲観値1/10=6名程度しか期待できず、防災要員は3公園に分散しても統制とれないでしょうから、全員が南公園へ集合にした。
- 組織の編成
- 改訂Aまでは、避難に関する組織を避難所設営、避難移送、避難生活の3つに細分していたが、これを平和時と同様に避難移送隊に統一した。
- 松風台の外に出ての避難活動は、湘北地区防災拠点(香川小学校避難所、鶴が台中学校医療避難所、スリーハンドレッドゴルフ場広域避難場所)となり、松風台自治会が単独行動は出来ないのでこの行動指針に含めず削除した。
- 防災要員の参集率
- 今後の検討課題として残っていること
- 松風台を離れて近隣地区へ避難する場合の具体的な方法
- 湘北地区では合同で毎秋に防災要素訓練は継続してきたけれども、本当に大災害が発生した場合に各自治会がどのように連携するのか下記の課題にはまだ具体的に取り組まれていません。
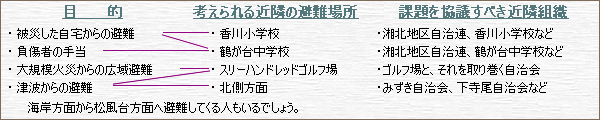
- 要援護者支援制度から避難行動要支援者支援計画への切り替え
- 茅ヶ崎市は災害対策基本法の改正に基づき、制度の切り替え全体計画が2017/4月に策定される予定です。
- 支援する側の活動に大きな変化はないと思われるが、最も高齢化の街としては引き続き重要課題です。
- その後、市の制度が要援護者から避難行動要支援者に名称変更されたが基本的な活動は同じである。
- 松風台を離れて近隣地区へ避難する場合の具体的な方法
- 茅ヶ崎市の用語との対比
この指針に用いた場所 茅ヶ崎市の防災用語 役割など 松風台南・東・西公園 一時避難場所 自宅から応急的に避難する近くの場所 松風台自治会館
(災害対策本部)地区活動拠点(本部) 自治会単位での地域活動拠点 香川小学校 災害対策地区防災拠点(避難所) 湘北地区からの避難者受入など 鶴が台中学校 災害対策地区防災拠点(避難所)
(救護避難所を兼ねる)地区活動拠点との連携
市対策本部との連絡調整スリーハンドレッドゴルフ場 広域避難場所 大規模な火災から一時的な避難場所 - 松風台の過去約10年間の防災活動を整理した参考資料
- 防災会だより第42号 2014.09.30 松風台の大災害~地震・火事などに備えて~
- 防災会だより第46号 2015.10.09 地震被害想定と防災活動への期待
- 防災会だより第48号 2016.03.31 松風台の防災活動~地震・火事に備えて その後の10年~
制定改訂履歴
| 制定改訂 | 年月日 | 制定のいきさつ、及び改訂箇所とその理由 |
|---|---|---|
| 制定 | 2009.03.15 | これは防災行動指針の制定改訂履歴に記載すべき内容であるが、書ききれなく別に設けた。 |
| 改訂A | 2012.04.15 | 東日本大震災の教訓を基に、防災体制見直し検討WGを設けて検討した結果を反映させた。 |
| 改訂B | 2017.03.12 | 行動フローなどを誰にも判りやすいように簡素化した。 |
| 改訂C | 2019.06.06 | 組織変更、白いタオル運動を反映させた。 |